🍙 米を噛むということ
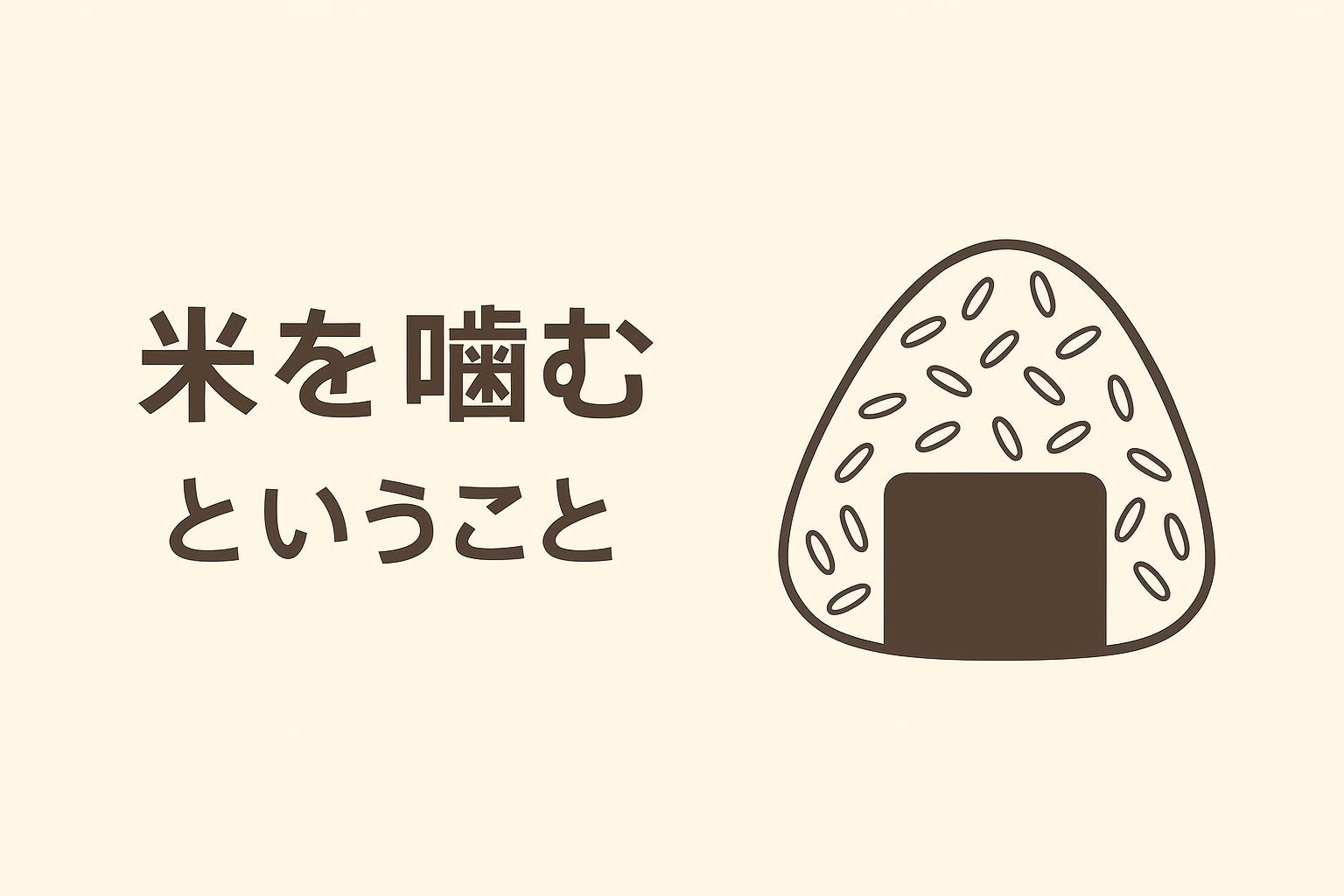
お昼に大きなおにぎりを2つ食べた。
おかずは たまご焼きとウインナー、あと柴漬け。
普段は軽めに済ませる昼食だが、今日はしっかりと食べた。なぜなら午後から庭作業が控えてたから。
◾️米はただの主食ではない
やはりここ一番で力を出したい時は“米”だなぁと常々思います。米は日本人にとって特別な存在。ただの主食ではない。噛むほどに心にまで染み渡るような力を持っている。
白米だけでももちろん美味しいけれど、私はそこに胚芽押麦を混ぜて炊きます。それは栄養の事を考えてというより、単純に“その方が美味しい”から。特に油ものとの相性が良く、麦の香ばしさが米の甘みを引き立ててくれます。
◾️ 米は生活の「安全保障物資」
最近は米の話題がどこかセンシティブになってきてます。価格の上昇、流通の不安、農家の高齢化。それでも私は静かにこう思ってます。
米は この国の “生活安全保障物資” だと。
飢えは国を壊す。逆に言えば、
食べものがあれば人は踏ん張れる。
◾️石高制度とコンバインと、誇りある仕組み
そう考えた場合、米づくりにもっと安定さと誇りがあってもいいかなと個人的には思います。たとえば昔のように、”収穫量”と”品質”に応じて評価される「石高制」のような仕組みはどうだろうかと。
それは田んぼの規模の大小に関係なく、地道に育てた人が収めた成果を比率に応じて補助や融資等で正当に報いるような仕組みがあれば、米作りにいっちょ人生を賭けてみようと考える人が今後増えるかもしれない。これはただの綺麗事なのだろうか。
私は農業の専門家ではないし、ひょとすると既に似たような制度や仕組みがあるかもしれない。しかし敢えてそれでも言葉にしてみたくなるのは、“誇り・実力・連帯”が三位一体となって結びついた仕組みが今、必要なのではないかと感じてます。
先述した「資本の大小に関係なく、真面目に育てているかどうか」で今後の融資や補助などの評価軸になるような形はどうか?
資本力の弱い小規模の田んぼの人たちは地域内の何人かで組んだ小さな寄合的な形でコンバイン等の高価機械の購入に対して融資交渉などが可能であれば、自分ひとりよりも少し大きな存在として活動できるのではないだろうか?
そして県の農業試験場やJAのような組織が、その橋渡しや助言役に回ることで、技術や資源が地域全体に行き渡る構図が出来ればあるいは…
米を育てる人たちは、すなわち
“この国の命の根っこ”を支えている人たちだから大切にしてもらいたい。
◾️ただの生活者の、ひそかな願い
もちろん私は政治家でも評論家でもないです。単なる”いち生活者”として毎日米を食べ、米に力をもらって生きている一人です。
しかしただ1点だけ、
私には心ひそかに願っていることがあります。
それは、
この国の祈りの場──たとえば新嘗祭のような場では、いつまでも国産の米が神前に捧げられますように、と。
それが当たり前でなくなってしまったら、
何かが静かに崩れていく気がしてなりません。
◾️米を噛む、その静かな時間
今日も米を噛んでいる。
それだけで肚がバンと据わり、
心の芯までスッと1本通った感覚がある。
たとえ時代がどう揺れても、
この感覚だけは、失いたくない。


